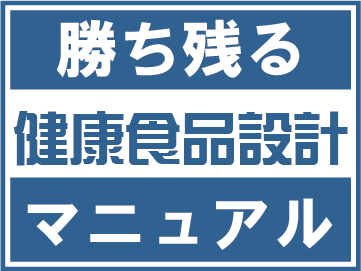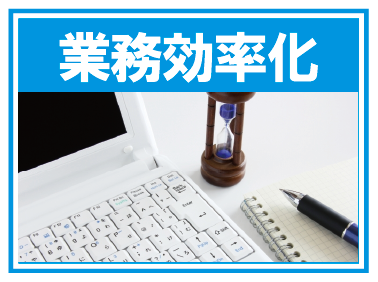この度、まめ鉄の供給条件に新条件を追加いたしました。
説明にもある通り、優良誤認/景品表示法違反のトラブルが止まりません。
最も多いのは、まめ鉄を下限値60mg(鉄として3mg)配合し、ピロリン酸第二鉄を7mg配合して、フェリチン鉄として鉄10mgの栄養機能食品として販売するというもの。
悪質なのは、全量がフェリチン鉄であるように見せるクリエイティブ。
まともに、まめ鉄由来の鉄だけで10mg配合している販売者さんがダメージを受けています。
もう一段階進むと、他の鉄素材との配合を禁止することになる。
悪質な販売者を排除することは、原料メーカーとして、やり過ぎのように思う人もいるだろう。
一方、こういった問題を放置すると、その素材の市場は荒廃し、必ず先細りしてしまう。真面目に売っている会社さんほど損をするし、多くの消費者が騙される。
加えて、まめ鉄を真面目に配合する会社さんが新規採用しなくなってくる。
結果、将来的に、弊社の原料事業に大きな打撃を与えることになる。
そのため、健全な市場育成のためにも、管理を徹底して、悪質な販売者を排除していく必要があるのです。
今の時代、市場が成熟しているため、どうしても、性悪説で動いていかないと、悪い売り方をする会社が出てきます。嫌な時代です。
説明にもある通り、優良誤認/景品表示法違反のトラブルが止まりません。
最も多いのは、まめ鉄を下限値60mg(鉄として3mg)配合し、ピロリン酸第二鉄を7mg配合して、フェリチン鉄として鉄10mgの栄養機能食品として販売するというもの。
悪質なのは、全量がフェリチン鉄であるように見せるクリエイティブ。
まともに、まめ鉄由来の鉄だけで10mg配合している販売者さんがダメージを受けています。
もう一段階進むと、他の鉄素材との配合を禁止することになる。
悪質な販売者を排除することは、原料メーカーとして、やり過ぎのように思う人もいるだろう。
一方、こういった問題を放置すると、その素材の市場は荒廃し、必ず先細りしてしまう。真面目に売っている会社さんほど損をするし、多くの消費者が騙される。
加えて、まめ鉄を真面目に配合する会社さんが新規採用しなくなってくる。
結果、将来的に、弊社の原料事業に大きな打撃を与えることになる。
そのため、健全な市場育成のためにも、管理を徹底して、悪質な販売者を排除していく必要があるのです。
今の時代、市場が成熟しているため、どうしても、性悪説で動いていかないと、悪い売り方をする会社が出てきます。嫌な時代です。